【FP監修】基礎年金底上げによる改定とは!?
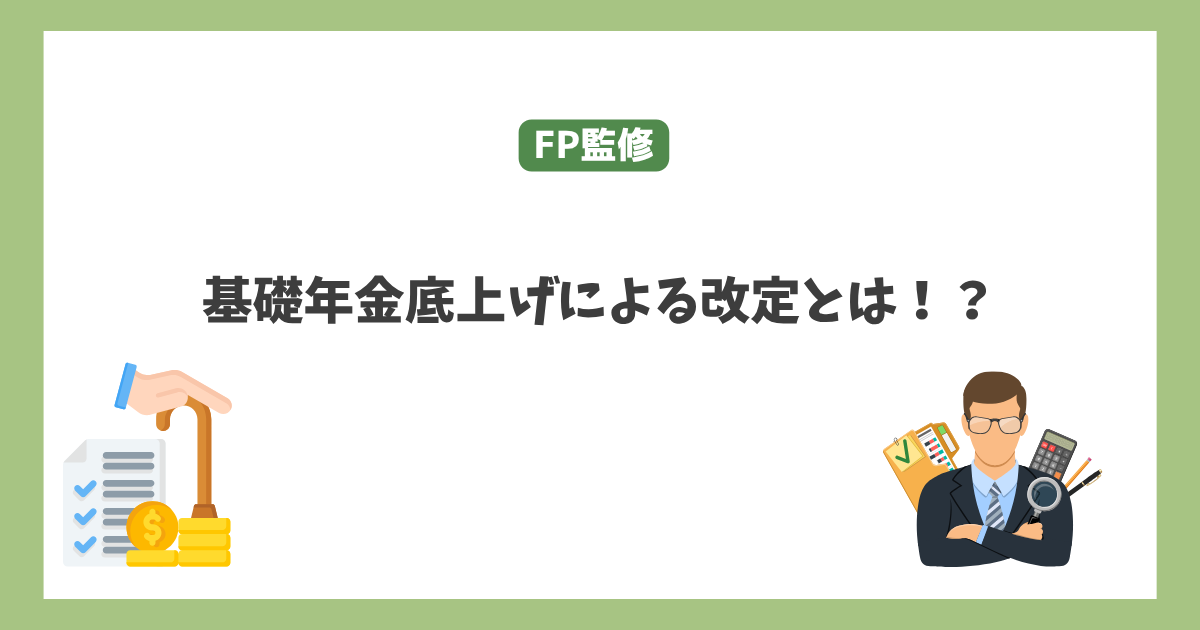
はじめに
みなさん、こんにちは。
今回のテーマは、定年退職後に受け取れる国民年金と呼ばれる基礎年金の制度が変わろうとしていることについて述べていきたいと思います。
今までの年金制度は1階建てと2階建てに分かれており、1階部分は国民年金(国民が全員加入)(以下、基礎年金と呼称)と2階部分は厚生年金(会社員が加入)に分かれています。
今回の制度改定では、昨今の物価高で、基礎年金額が物価上昇率に追いついておらず、厚生年金が受け取れない個人事業主などが老後大変なことになってしまうため、この基礎年金と呼ばれるベース部分の底上げを検討することになりました。
しかし、この底上げも容易ではなかったようです。
それもそのはず、国民全員の基礎年金の底上げということになるので、膨大な費用を計上しなければならないからです。
そこで政府は、その費用をどこから捻出を検討したかというと、我々が納めている厚生年金保険料から一部徴収して基礎年金を上げるというもの。
これには、多くの厚生年金保険料を納めている国民からは大反発です。
それは当然でしょう……
ぜなら、こうなることによって、自分たちの老後の年金が減らされることを意味するからです。
基礎年金の費用捻出について
ただ今までもこの基礎年金の費用捻出に関しては話し合いは行われてきました。
たとえば、今回のように厚生年金保険料からの徴収や国民年金保険料支払い期間を現行の20~60歳までの40年間ではなく20~65歳の45年間に引き延ばすなど、様々な案が出たようです。
しかし、案が出ては消え出ては消えの繰り返しでこのまま時が経過してきました。
そして、今回おそらく高確率で基礎年金の引き上げるための捻出費用の出どころは厚生年金保険料から徴収することにほぼ確定しそうです。
結果として、厚生労働省は全ての国民が受け取る基礎年金(国民年金)の給付水準を底上げする方針で、基礎年金だけに入る自営業者(個人事業主含む)らが老後に受け取る年金の水準低下を防ぐことになりました。
基礎年金の財政状況が厳しい一方、会社員らが入る厚生年金は堅調なため、厚生年金の積立金(剰余金)を基礎年金の給付に振り向けることになりました。
こうすることで2036年度以降の給付水準は現在の見通しより3割程度改善するようです。
厚労省は、厚生年金受給者の大半も給付が手厚くなるとしているが、保険料を折半して負担している会社員や企業の反発も予想されます。
社会保障審議会の部会で議論を進め、25年の通常国会に制度改革関連法案の提出を目指しています。
基礎年金の財源の半分は国庫(税)で賄っています。
そして、給付水準を改善する場合、追加で必要となる国庫分は40年度は5千億円、70年度には2兆6千億円にのぼります。
財政が安定化するまで「マクロ経済スライド」という仕組みで給付水準を抑制しています。
給付水準は「現役世代の手取り収入と比べた年金額の割合」で表され、24年度は約60%。うち基礎年金部分が30%半ば、厚生年金部分は25%。
現行制度のままだとマクロ経済スライドによる抑制が57年度まで続き、以降の水準は約50%(基礎年金約25%、厚生年金約25%)で下げ止まる計算です。
厚生年金は横ばいですが、基礎年金は3割目減りします。
厚労省によると、厚生年金の積立金は23年度末時点で243兆円。基礎年金に活用した場合、給付水準は36年度に約50%半ばとなり、うち基礎年金部分は3割程度改善します。
マクロ経済スライドによる抑制は36年度で終わるため、以降は給付水準が下げ止まります。
ただそうなると、基礎年金だけでは昨今の物価上昇に追いつけず、いくら基礎年金の底上げを図ったとて、少子高齢化により基礎年金の給付も多くなってくると見込まれるため、基礎年金の引き上げだけでは、年金のみの生活は困難と予想されます。
そのため、今ある制度でNISA制度やiDeCo制度を活用して、基礎年金に上乗せする形で推奨している姿勢は変わりません。
まとめ
国の制度は、年金制度だけではなく、あらゆる方面で制度変更があります。
つまり国は、一生涯制度保証をしているわけではないのです。
これは個人的な意見にはなりますが、国の制度には頼り過ぎず、自助努力で今後の解決策を模索してほしいと考えます。
しかし、ひとりですべてを解決するのは大変だと思うので、ぜひ一度ファイナンシャルプランナーなどお金の専門家に相談してほしいと思います。
みなさんの今後が豊かな生活になることを心から願います。
 監修FP
監修FPライフプラン表を無料でプレゼントしております!
是非一度、ご相談ください。
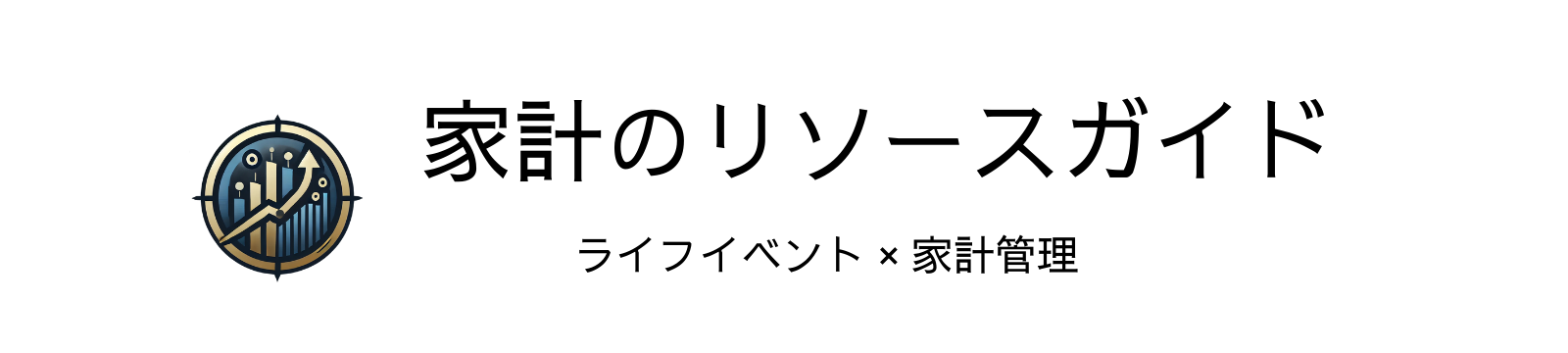
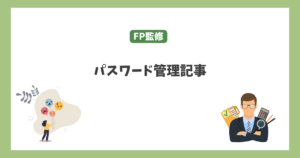
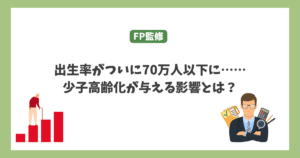
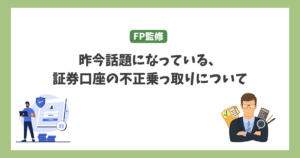
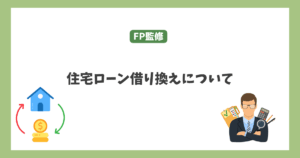
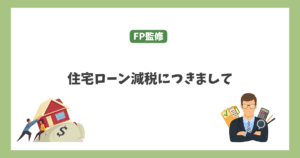
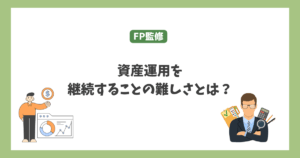
コメント